気になるあの人の本棚
がんと向き合った人たちから、心に残る本をご紹介いただきます
桜井なおみさん(患者支援団体代表)の一冊
『死を見つめる心』岸本英夫著

自分が「生きることに飢えている」と
気づいたとき
はじめて心を整えることができた
自らのがん体験を記して著書にした医師が
すすめてくれた一冊
乳がんと診断されてから1ヶ月ぐらいたったころに、竹中文良先生(当時日本赤十字社医療センターの外科部長)に紹介していただき、手にしたのが『死を見つめる心』(岸本英夫著 講談社文庫)です。
父が膵臓がんと診断されたとき、「がんを告知しなくてはいけない人(医師)が患者の立場に立ったとき、どう感じたのだろう」と思って読んだのが、竹中文良先生の『癌になって考えたこと』(文春文庫)です。この本を読んで「医者も動転する」ということを知り、それなら家族や本人が動転するのは当たり前だなと思いました。そして、最初は家族として、私ががんと診断されてからは当事者として、竹中先生とお会いしました。「先生の本を読みました」とお伝えしたところ「いや。私の本じゃなくて他の本、読みなよ」と言って紹介してくださったのが『死を見つめる心』でした。
がんと診断されると、自分の死を身近に感じます。「死ぬことと生きることは背中合わせ」ということを、ものすごくリアルに感じるわけです。ひょっとしたら次のオリンピックは見られないかもしれない、って本気で考えます。どうやってこういう気持ちを乗り越えていくのだろう、どうやって心を整えようかな、と思ってさまざまな本を読みました。セーレン・キルケゴールやジャン=ジャック・ルソーなどの哲学書や宗教に関する本を手にとり、むさぼるように読んでいたとき、「あ、ここだったんだ」と自分の中でたどり着いたと感じたのが、この本です。
こんなにも悩んだり、もがいたりするのは、「生きたい」という渇望があるから
『死を見つめる心』は、宗教学者である岸本英夫さんが、皮膚がんと診断されてからの10年間に発表したものをまとめた本です。三部に分かれていますが、私がもっとも心揺さぶられたのは、第一部の「死に出逢う心がまえ」です。ここに、この本のすべてが凝縮されていると思いました。
「生命飢餓状態におかれて」1
岸本さんは、がんの宣告をされたときに、この「生命飢餓状態」が始まったと言っています。
「生命飢餓状態というものは、生存の見通しに対する絶望がなければおこってこないというところに、大きな特徴がある。」2
「生命飢餓感は、食物に対する生理的な飢餓感に酷似している。」3
と記しています。
この『生命飢餓状態におかれて』という言葉が、私の心にすっと入ってきました。
進行がんで病状がやや進んでいるうえに若いから5年生存するかはフィフティーフィフティー、と私は医師から言われていて、その突然の不確かな生の中にいて、なんでこんなに自分はこんがらがってしまっているんだろうとずっと思っていました。でも、この文章を読んで、「あ、自分は生きることに飢えているからなんだ、生きたいんだ」ということに気づいたのです。そして、それはごく自然な状態であるということもわかりました。
岸本さんは宗教学者で、本の中でご自身のことを「人間一般の死の問題について考えようとする立場である。これは、いわば、一般的かつ観念的な生死観である。」4と語っています。そして「もっと切実な緊迫したもう一つの立場がある。」5とし、「それは自分自身の心が、生命飢餓状態におかれている場合の生死観である。」6と語っています。
これまで死の問題について、岸本さんは宗教学者として観念的な生死観で考えてきたけれど、自分ががんと診断されてみたら、観念的な生死観で考えているときの死と、実際に死が背中合わせになったときに感じる死というのは全然違うということを感じたのだと思います。読んでいて、岸本さんはとても正直な人だなと思いましたし、私がいくら精神論の本を読んでもピンとこなかったのは、自分が感じているリアリティとの差があったから、ということがよくわかりました。
1.4.5.6.『死を見つめる心』(岸本英夫著 講談社文庫)P11
2.『死を見つめる心』(岸本英夫著 講談社文庫)P12
3.『死を見つめる心』(岸本英夫著 講談社文庫)P13

心を煩わすべきは命のあるかぎり、
最後までどのように生きるかということ
本を読み進めていくと、岸本さんが、自分の経験として肝に銘じて知ったこととして記したいろいろな言葉に出会います。この言葉の一つ一つが、私の心に突き刺さっていきました。
「死の場にたって、はじめて、命の尊さを知り、そこに腹をすえて、人生を見直す」7
「人間が生きてゆくために心を煩わすべきは、死の問題ではなく、この大切な人間の命を、どうするか、どう生きてゆくか、ということ、命のある限り、その最後の瞬間まで、どうよく生きてゆくかということを、常に考えなければならないということであります。」8
「つらくて、苦しくても、与えられた生命を最後までよく生きてゆくよりほか、人間にとって生きるべき生き方はない。」9
赤裸々に、わかりやすい言葉で書いてあります。観念とは全然違う、リアルな言葉です。「私が求めていた言葉がここにある」と思いました。読みながら心に響く部分に赤い線を引いていたのですが、ほとんどのページが真っ赤になりました。
がんと診断されてから「なんで、自分がこんな病気にならなくてはいけなかったのか。ひょっとしたら死んでしまうのではないか」と思うとき、私はとても怖くなり、悩みました。しかし、この本を読むことで、自分の今の状態を客観的に見ることができ、私の心は整っていきました。エリザベス・キューブラー・ロスによる死を目前に控えた人の心理過程(5つの段階)の「受容」とはちょっと違うかもしれませんが、「ああ、そうなんだ」と納得できたのです。
7.『死を見つめる心』(岸本英夫著 講談社文庫)P36
8.『死を見つめる心』(岸本英夫著 講談社文庫)P37
9.『死を見つめる心』(岸本英夫著 講談社文庫)P22
病気になってから手放してもよいものと
いけないものがあることに気づいた
振り返ると私にとって必要だったと思う本が、もう一冊あります。千葉敦子さんが書かれた『「死への準備」日記』(朝日文庫)です。
この本は、当時朝日新聞に連載されていた絵門ゆう子さんのコラム「がんとゆっくり日記」で知りました。絵門さんは、転移性乳がんの治療中でした。がんの進行に対しては抗っているけれど、一方で自分の生活や大切にしたいことを絶対手放さない。そんな絵門さんの文章を、私はすがるように読みました。
絵門さんは、自立した女性としてどう生きていくかということが記された千葉敦子さんの著作本についてもコメントを寄せられていました。私も読んでみようと思ったのですが、自分と同じ部位の乳がん患者さんの本は、治療を受けているとやはり怖くてなかなか読むことができませんでした。勇気を出して読んだのは、診断されてから1年くらい経ったころです。
そのころの私は、復職したばかりで、100パーセント元通りには動かない身体や心を抱えて、「これから自分の仕事をどうしようか」、「自分にとって働く意味はなんだろう」ということをずっと考えていました。また、同世代の友達を亡くし、親以外の人が「がん」で死にゆくさまを初めて近くでみるという喪失体験をしました。その友達はがんと診断されていて、亡くなるギリギリまで仕事をしていました。
この本を読んで、1番最後のページ(単行本に収録された内容の最終ページ)で、私はやられたなと思いました。
「体調悪化し原稿書けなくなりました。多分また入院です。申しわけありません。」10
詫び文ですが、これが仕事をする人そのものだ、と思ったのです。たとえ病気があろうとも、責任を果たして、役割に対して応えていくのが仕事をする人の姿なのだと思いました。そして、このことが千葉さんのモチベーションにもなっていたし、彼女のレガシーでもあるように感じました。
私は、この文章を読んで、申しわけないなんて思わなくてもいいような社会になるといいと思いました。その一方で、このような責任感や覚悟をもっていないと病気をもちながら仕事はできない、ということも思いました。
「自分はここまで責任を果たしていけるのか、覚悟はあるのか」と、深く考えました。これから先、仕事を受けても、5年後にその業務ができなくなる可能性もあるわけです。そこで「仕事ばかりの人生でよいのだろうか。1回足を止めて、ちょっとカバンを置いてみよう」と思いました。部下やクライアントをもつというのが、重かったのです。重たいカバンを降ろして、ちょっと楽になりたいと思いました。
そして、いざカバンを降ろして、仕事をやめてみたら、驚いたことに自分の中の仕事の意味が強烈に鮮明になってきました。楽になりたかったのですが、降ろしたほうが辛くなってしまったのです。病気になって手放してよいものと、手放してはならないものがあって、仕事や社会との関わりは決して最後まで手放してはいけなかったんだ、いうことに気づきました。
今でも、この本の最後のページはよく思い出します。まだ現役で働いている間は、自分の拠り所になるのではと思っています。
10.『「死への準備」日記』(千葉敦子著 朝日文庫)P224

治療は生きるためにある。日常生活を手放さず、自分の道は自分で決める
もう1つ、この本の中ですごくいいなと思ったことは、だんだん体調が悪くなっていくけれど、日常生活を手放さない千葉さんの姿です。これは絵門ゆう子さんにも重なるところがあります。
「治療のために生きるのではなくて、生きるために治療している」と、千葉さんは言います。そうでないと、がんに全部奪われてしまうと、私は思いました。
周囲の人の関わり方もすごくいいのです。千葉さんはニューヨークに住んでいるのですが、まわりの人は、彼女ががんに罹患していることを知っていても気にせず普通に食事や映画に誘ってきますし、ホームパーティーもするし、彼女もそこに普通に飛び込んでいく様子が書かれています。日本だったら、腫れ物に触れるような感じになってしまうかもしれません。
私は、がんと診断されてすぐに、「私がんになったよ」と300人もの人にメール出したのですが、5通程度しか返信が来ませんでした。「世間は冷たい! 友人も冷たい! しょせん、病気なんて他人事なんだ!」と、ショックを受けていたのですが、そのあと、友人から連絡があって、メールを受け取った人の気持ちがわかりました。どう返事をしていいのかわからず悩んでいたのです。ボタンのかけ違いがあったことに、私は気づきました。
自分の病気のことを開示していくのは、大変なことです。また、聞いたほうも、いろいろ考えすぎて、返す言葉が見つからない、ということがあります。
「がんになったよ」と友達から言われると、私もどう返していいのかいつもすごく悩みます。考えれば考えるほど返す言葉がなくなってしまいます。
でも、「返す言葉がない」と相手に言っていいんだと、今は思っています。「驚いて返す言葉がないです」という自分の気持ちをそのまま伝えることが大切だということが、今ならわかります。びっくりしたら「びっくりした」、「すごく驚いて心配している」と言うようにしています。
病気の治療にとって、周りの人とのコミュニケーションや関わり方は、重要なファクターの一つであると感じています。
最後に
『死を見つめる心』は、とくに20〜40代の若い人におすすめしたいです。どうしても周囲の人と比較してしまい、自分だけ足を止めてしまっている、その不条理さをどう考えていこうかな、と悩んだときにヒントがあるように思います。
『「死への準備」日記』は、とくにがんとキャリアについて悩んでいる人、バリバリ働いている人が読むと役に立つでしょう。
そして、もう一つ。がんと診断されたら、自分のがんのことが書いてある本を、薄いものでいいので、発行年月日が比較的新しいものを一冊用意することをおすすめします。これは、私の主治医から言われたことです。「医学っていうのは難しい単語がいっぱい出てくる。気をつけながら話しているけれど、どうしても説明しきれないところがある。まだまだ若いから、これから先の治療や生き方を一緒に決めていかなければならない。分厚くなくてよいので、一冊でいいから、がんの本を読んでください」と、当時の主治医は言いました。そして書店で購入したのが『乳がん 私らしく生きる』(財団法人パブリックヘルスリサーチセンター編 ライフサイエンス出版)でした。本の表紙の帯には「乳がん? だいじょうぶ、作戦会議、開きましょう」とあり、この「作戦会議」という言葉に「なるほど」と思いました。先生が言っていることはこのことなのかと確認をしたり、診察から帰ってきてからもう1回読み直してみて、わからなかったことを次の外来時に聞いたりしていました。すると、自分が今どこにいるのか、次に何を決めなくてはいけないのか、ということがわかってくるのです。安心につながりました。
今は、患者さん向けのガイドラインがありますので、まずはその中で自分の関わるところだけ、今心配なところだけでいいので、読んでみることをおすすめします。

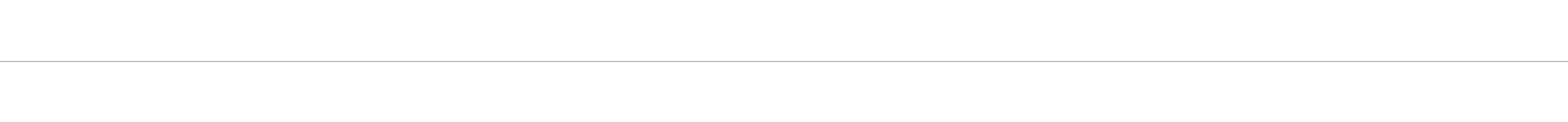
桜井なおみさんの本棚から3冊をピックアップ!

『死を見つめる心』
岸本英夫著 講談社文庫
人間が死というものに直面したとき、どんなに心身がたぎり立ち、猛り狂うものか――すさまじいガンとの格闘、そしてその克服と昇華……言語を絶する生命飢餓状態に身をおいた一宗教学者が死を語りつつしかも、生きることの尊さを教える英知と勇気の稀有な生死観。第18回毎日出版文化賞受賞。

『「死への準備」日記』
千葉敦子著 朝日文庫
NYでジャーナリスト活動を続けていた著者が、3度目のがん発病の経過を、死の2日前まで書き綴った日記。

『乳がん 私らしく生きる』
財団法人パブリックヘルスリサーチセンター編 ライフサイエンス出版
乳がんと診断され不安の中にある患者さんに、まずは手に取って欲しい乳がん治療に関する基礎知識の本です。知っておきたい標準治療と最新治療、手術、乳房再建、化学療法・ホルモン療法・抗体療法、放射線治療、治療に伴う諸症状への対策、医療費、情報入手のコツ、日常生活の工夫など、各患者さんが自分らしく生きることをサポートする内容になっています。また患者さんの声を交えながらわかりやすく解説しています。
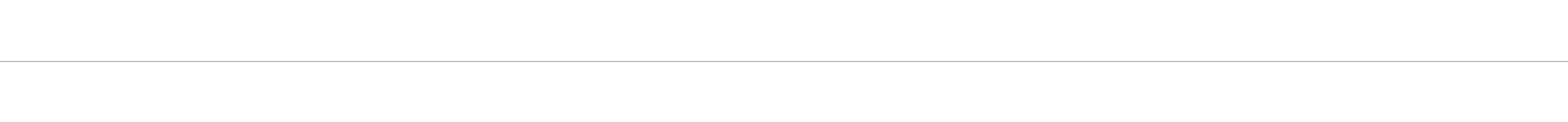
桜井なおみ さくらいなおみ
患者支援団体代表。大学で都市計画を学んだ後、卒業後はコンサルティング会社にてまちづくりや環境学習など「人と都市をつなぐ」活動に従事。2004年、30代に乳がんを罹患した後は、自らのがん経験や社会経験を活かし、小児がんを含めた働く世代の患者・家族の支援活動を開始、「患者・家族と医療をつなぐ」を展開中。「何かと何かをつなぐこと」を人生のテーマにすることを見つけ、現在も活動中。キャンサーソリューションズ㈱代表取締役社長、一般社団法人CSRプロジェクト代表理事、NPO法人HOPEプロジェクト理事長。技術士(建設部門)、社会福祉士、精神保健福祉士、産業カウンセラー。第21回人間力大賞会頭特別賞受賞など。

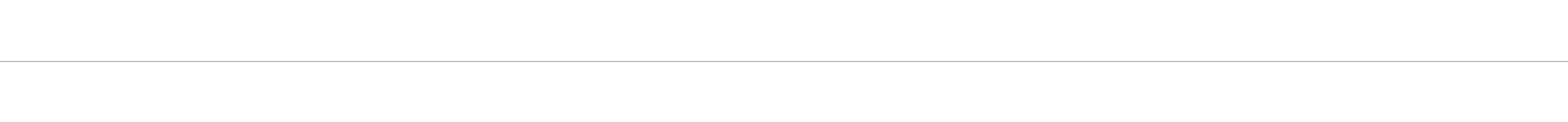
「がん&」編集部から桜井なおみさんの著作本をご紹介

『あのひとががんになったらー「通院治療」時代のつながり方』
桜井なおみ著 中央公論新社
入院から通院へ、治療の中心が移る「がん」。がん患者本人はもちろん、取り巻く私たちの環境にも大きな変化が起きています。家族や友人、同僚から「がんになった」と聞いて、あなたはどう答える? 自治体や国が働くがん患者の支援に注力を始めるこれから、職場はどんなサポートをすればいい? 家庭や会社はもちろん、社会全体で新しいコミュニケーションが必要とされる今、変えるべきはきっと「意識」です!
取材日:2022年6月28日
編集・取材・執筆:早川景子